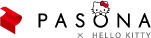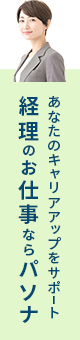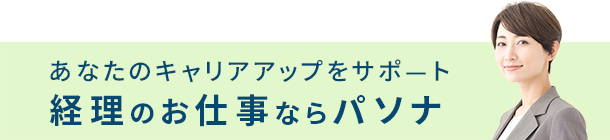経理の勉強方法は?実務で必要な知識から独学での学習方法、おススメ資格をキャリア別に紹介

経理として働く方の中には、お仕事の幅を広げてキャリアアップを目指している方もいるでしょう。
キャリアアップを叶えるためには、具体的にどのような勉強や資格取得をすると良いのでしょうか。
今回は、経理のキャリアを「未経験者」「初心者」「中級者」の3つのステップに分けて、必要なスキルや資格、勉強方法についてまとめました。上級者を目指すためのポイントも紹介していますので、キャリアアップに役立てみてください。
パソナでは、お仕事の悩みや疑問を未登録の方でもご相談できる、アバターキャリアコンシェルジュというサービスがあります。キャリアに関するご相談だけでなく、気軽なご質問やご相談も可能!キャリアコンサルタントがアバターを通じてご質問にお答えします。
- 目次
- 【未経験者】お仕事スタートまでに身につけておきたい基礎スキル
- 経理基礎スキル 勉強のポイント
- 【初心者】日商簿記3級レベル(日常経理・月次補助)
- 日商簿記3級 勉強のポイント
- 【中級者】実務経験を積み、日商簿記2級レベル(月次・年次決算)へステップアップ
- 日商簿記2級 勉強のポイント
- 日商簿記合格に向けた3つの学習方法
- 経理におススメの資格
- 経理の資格に関するQ&A
- 資格を取得して、着実なキャリアアップを目指そう
【未経験者】お仕事スタートまでに身につけておきたい基礎スキル
経理職は会計データの入力、計算、請求書・納品書の作成や確認など、数字を扱うことが多いお仕事。
スピードと正確さが求められ、時には膨大なデータの集計や分析を任されることもあります。
これまで経理に必要な勉強をしてきた方も、自信を持って業務に臨むために就業前には、復習をしておくのがおススメです。就業前に復習しておきたい、経理の基礎知識やスキルについて紹介します。
※関連ページ:経理・財務で働く | パソナ
経理の基礎
まずは、お仕事で必須となる簿記の基本知識をおさらいしておきましょう。
取引
簿記上の「取引」とは、お金やモノ(会社の商品や資産)が増えたり減ったりすることを意味します。
具体的には、実際に商品を購入したり、手続きを行ったりしたことで「会社の資産、負債、純資産(資本)、収益、費用が増減すること」が取引にあたります。
仕訳
「取引」を記録する手段が「仕訳」です。仕訳をスムーズにできるようになるには、「5つのグループと勘定項目」を覚えて「借方」「貸方」を理解することが重要です。
「借方」「貸方」とは、取引があったときに記帳する仕訳の勘定科目の位で、伝票の左側に「借方」、右側に「貸方」を記入します。
5つのグループと勘定項目
簿記においての各取引を「資産・負債・資本・収益・費用」といった5つのグループに分けて勘定項目を記載していきます。
会社を出入りするお金をカテゴリ別に分け、勘定科目というインデックスをつけていくイメージです。

- 資産…現金や預金、売掛金などの事業における資金・資産
- 負債…借入金や買掛金、未払金など返済が発生するお金
- 資本…株主から預かった資本金など事業の元金
- 費用…人件費や接待交際費など事業を営むのに使われるお金
- 収益…売上高や雑収入など事業収入全般
決算書(貸借対照表・損益計算書)
決算書とは、会社のお金の状況を表す書類のことです。毎年、社内外に向けて事業年度における会社の成績を発表・開示しなければなりません。
一般的に決算書は、「貸借対照表(B/S)」「損益計算書(P/L)」「株主資本等変動計算書」「キャッシュフロー計算書」の4つから構成されています。
このうち重要なのが、「貸借対照表(B/S)」「損益計算書(P/L)」という書類です。
貸借対照表には、会社の資産と負債のバランスをまとめたデータが記載されています。一方、損益計算書は、会社の1年間の損益を計算した計算書のことを指します。
この貸借対照表や損益計算書でよく使用される基本的な勘定科目は、あらかじめ覚えておきましょう。
また、それぞれの書類の見方についても、就業開始前までにおさらいしておくと良いでしょう。
Excelの基礎知識やショートカット
経理職では、Excelや会計ソフトを使ったデータ入力や集計作業が主な業務になります。参考書などを見ながら、基本操作や便利なショートカットなどをマスターしておきましょう。
電卓のタッチタイピング
最近はExcelや会計ソフト上での作業が主流ではありますが、伝票や領収書の処理など、簡単な計算は電卓を使ったほうが早い場合もあります。
早打ちの練習を行うことで、電卓の計算スキルは確実に上達します。また、日常業務の作業効率もアップするでしょう。
経理基礎スキル 勉強のポイント

紹介してきた、経理基礎スキルを身につけるためには、何から勉強を始めれば良いのでしょうか。
経理の知識、Excelスキル、お仕事に使う電卓選びの3つに分けて紹介します。
1. 経理の基本業務を知る
仕訳の練習
まずは簿記の基礎内容を学習します。その後に、実務に備えて「仕訳の練習」をしてみましょう。
貸借対照表・損益計算書を見て基本的な勘定科目を把握
会社の財務状況を知るための「貸借対照表(B/S)」
会社の利益を確認するための「損益計算書(P/L)」
これら2つの作成は、経理にとって欠かせない業務です。特に「貸借対照表」は慣れないうちは複雑に感じることもあるので、就業前に貸借対照表のサンプルをしっかり読み込んでおきましょう。
参考書を繰り返し見ておくのがおススメです。
2. Excelの基本スキルを磨く
経理のお仕事では、Excelを使った数字集計や資料作成業務が多くあります。就業前にExcelの基本スキル+αをマスターしておけば、作業の効率もアップし、より活躍の幅が広がります。
計算がスムーズになる関数や、集計作業で役立つピボットテーブルなど業務で役立つExcelのテクニックを紹介します。
基本的な計算の関数
- SUM関数:=SUM(参照範囲)
- AVERAGE関数:=AVERAGE(参照範囲)
- MIN関数:=MIN(参照範囲)
- MAX関数:=MAX(参照範囲)
- COUNT関数:=COUNT(参照範囲)
指定したセル内の数字を合計します。
指定したセル内の数値の平均を出します。
指定した範囲のセル内の数値の最小値を出します。
指定した範囲のセル内の数値の最大値を出します。
空白以外のセルの数を数えてくれます。
集計で役立つ関数
- IF関数:=IF(論理式,[値が正しい場合],[値が誤りの場合])
- AVERAGE関数:=AVERAGE(参照範囲)
- VLOOKUP関数 :=VLOOKUP(検索値,検索範囲,列番号,検索方法)
- SUBTOTAL関数:=SUBTOTAL関数(集計方法,参照範囲)
- ピボットテーブル
条件を満たす内容のセルを数える関数。テキストや数値、計算式が条件として指定できます。
テキストを指定する際は、ダブルクォーテーション「“”」で囲みましょう。
指定したセル内の数値の平均を出します。
指定した範囲の中から、検索条件に合うデータを探し出してくれる関数。
「検索する値」や「検索する範囲」などを入力するだけで、膨大なリストの中から必要なセルが簡単に見つかります。
合計や平均などの数値を集計するのに使える関数。引数を変更すれば、平均値や最大値なども簡単に計算できます。表の間に小計がたくさん含まれ、最後に総合計を求めるような表を作成する場合に便利な関数です。
Excelの基本的な集計機能。作成した表の項目を選択するだけで、クロス集計や平均値算出、データ集計の詳細化などが簡単にできます。
Excelのテクニックを習得するには、参考書を見ながら繰り返し作業を練習することが大切です。実際に操作をしながら、習得を目指しましょう。
3. 自分に合った電卓を選ぶ
経理のお仕事を始めるときには、使いやすい電卓を準備しましょう。
電卓選びのポイントは、タッチタイピング(ブラインドタッチ)でキーを押せるサイズ感、効率的な計算を助けるメモリーキーなど、次の4つです。
- 自分の手になじむサイズ感のもの
- 12桁以上表示できるもの
- 数字が大きく見やすいもの
- GT(グランドトータル)キーとメモリーキーがあるもの
なお、簿記の試験会場には以下の機能がついた電卓を持ち込むことができません。簿記検定の資格取得を目指しているは、注意しましょう。
- 印刷(出力)機能があるもの
- メロディー(音の出る)機能があるもの
- プログラム機能があるもの(例:関数入力などの機能がある電卓、売価計算・原価計算の公式記憶機能がある電卓)
- 辞書や文字入力の機能があるもの
【初心者】日商簿記3級レベル(日常経理・月次補助)
経理アシスタントのお仕事は、仕訳や伝票起票・計上、現預金の管理、手形管理、売掛・買掛管理、帳簿の作成といった日常的に発生する業務がメインとなります。
まずは日商簿記3級の資格取得に挑戦し、さらにキャリアアップを目指す方は、月次決算の補助業務などにもチャレンジしていくと良いでしょう。
日常経理のお仕事サイクル例
| 8:50 | 出勤 |
|---|---|
| 9:00 | 1日の予定や連絡事項の確認、メールチェック |
| 9:30 | 売上の入金・支払い状況の確認、出入金確認、銀行での通帳記帳 |
| 11:00 | 取引伝票の起票・整理 |
| 12:00 | 休憩 |
| 13:00 | 経費精算処理、現金小口確認 |
| 15:00 | 仕訳業務(会計ソフトへの入力) |
| 17:00 | 書類のファイリング(処理が終わった請求書や領収書など) |
| 18:00 | 明日の予定の確認や準備をして業務終了 |
日商簿記3級 勉強のポイント

日商簿記3級は、経理担当者だけでなく、営業職や管理部門の方も多く受検している検定試験です。
出題範囲は、簿記の基本原理や各種取引の処理方法、決算書類の作成など。商業簿記・会計学の基礎を習得できるため、幅広いビジネスパーソンに役立つ汎用性の高い知識が身につく資格です。
学習時間の目安と出題範囲
日商簿記3級の学習時間目安は、約70~100時間と言われています。
合格率は40%~50%程度で、初心者でも比較的取得しやすい資格と言えるでしょう。
範囲は、商業簿記の原理(仕訳・帳簿記入など)、各種取引の処理、決算(試算表の作成など)から出題され、70点以上で合格となります。
勉強のポイント
日商簿記3級は、独学でも取得しやすい内容のため、市販のテキストでの学習がおススメです。
まずはテキストをしっかりと読み込んで、簿記の基本となる考え方や仕訳の仕組みを覚えましょう。電卓を片手に、過去問を繰り返し解いてみてください。
【中級者】実務経験を積み、日商簿記2級レベル(月次・年次決算)へステップアップ
日々のお金の流れに関わる日常経理業務をマスターしたら、次は“一人で月次決算処理ができる”レベルの「日商簿記2級」を目指しましょう。
経理アシスタント職からステップアップしたい方や、次のレベルに挑戦したい方におススメです。
また、日商簿記2級以上を求人の応募条件としている企業も多いため、取得すれば挑戦できるお仕事の幅がさらに広がります。
簿記の基礎や実務の知識がきちんと身についているか、業務と並行して確認しながら、日商簿記2級の学習を進めると良いでしょう。
月次・年次経理のお仕事サイクル例
月間スケジュール
| 上旬 | 取引先からの入金確認、経費精算、月次決算整理、月次決算書作成、源泉所得税、住民税の納付 |
|---|---|
| 中旬 | 1日の予定や連絡事項の確認、メールチェック、現金の出納管理、伝票起票・計上、仕訳、経費精算、領収書の管理などの日常業務、在庫・資産の確認などの決算に向けた準備 |
| 下旬 | 給与計算・支払い、請求書発行、取引先への支払い、社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)の納付 |
年間スケジュール(3月決算の場合)
| 4月 | 決算整理、台帳繰越作業 |
|---|---|
| 5月 | 税務申告・納付、決算書作成、決算発表 |
| 6月 | 株主総会準備、有価証券報告書の提出、決算公告 |
| 7月 | 夏季賞与の計算・支給、社会保険の各種手続き |
| 8月 | 夏季休暇の影響で営業日数が少ないため、日常経理・月次経理に専念 |
| 9月 | 中間決算準備 |
| 10月 | 中間決算書作成 |
| 11月 | 中間申告、税務申告・納付 |
| 12月 | 冬季賞与の計算・支給、年末調整 |
| 1月 | 源泉徴収票、給与支払報告書、法定調書合計表の作成・提出 |
| 2月 | 次期予算立案 |
| 3月 | 次期予算確定、決算準備、実地棚卸し |
日商簿記2級 勉強のポイント
日商簿記2級では、3級で学んだ商業簿記に加えて、新たに工業簿記が加わります。
原価計算や財務諸表作成、連結会計など、企業会計の知識をより深めることで、会社の経営状況を把握できるようになるでしょう。
学習時間の目安と出題範囲
中規模の株式会社を想定した商業簿記および工業簿記(原価計算)の内容が出題範囲です。
商業簿記が60点満点、工業簿記が40点満点で、2科目の合計が70点以上で合格となります。
日商簿記2級では、3級の出題範囲をベースにしながら、工業簿記におけるコスト管理についての知識が問われます。実施回によって異なりますが、合格率は15%~20%程度です。
合格に要する標準学習時間は、独学で約200時間とも言われています。
勉強のポイント
まずは2級のテキストや過去問に一通り目を通してみて、独学が大変そうだと感じる方は、資格取得のための専門スクールや社会人向け講座、eラーニングなどの受講を検討してみてください。
試験の出題範囲の傾向などを知ることができ、共に励まし合う仲間に出会える可能性もあります。
日商簿記検定の試験は年3回行われるので、試験日に合わせてスケジュールを組むと良いでしょう。
日商簿記合格に向けた3つの学習方法
資格取得のためには、自分に合った学習方法を選ぶことが大切です。
「どんな環境が勉強しやすいのか」「勉強にかけられる時間はどのくらいなのか」を考えながら、ベストな学習方法を選びましょう。
1. テキスト・参考書
日商簿記は経理の基本となる資格なので、書店でさまざまなテキストや解説本が販売されています。
気になるテキストをいくつか比較して、自分が読みやすいものを選びましょう。
テキスト選びに迷ったときは、レビューサイトや書店スタッフがおススメしている人気のテキストを選ぶのが無難です。テキストをフル活用して、自分のペースで学習を進めていきましょう。
2. スクール・講座
お仕事をしながら資格取得を目指す場合、効率を重視して学習を進めたいという方も多いはず。
そんな方には、資格取得のためのスクールや社会人向け講座がおススメです。
試験直前の短期集中講座や、じっくり学べる長期講座など、希望に応じて選びましょう。
通学のメリットは、指導経験が豊富な講師から直接、学習ポイントの指導を受けられるほか、分からないことがあればすぐに質問できることです。最新の試験傾向を踏まえたテキストを元に勉強できるので、試験対策にも有効と言えます。
3. eラーニング
「テキスト学習をコツコツ続けるのは苦手だけれど、スクールに通う時間の余裕がない」という方には、インターネットを利用したeラーニングがおススメです。
オンラインの学習プログラムや動画、アプリなどを使えば、24時間好きなときに、どんな場所にいても学ぶことができます。通学のスクール・講座に比べて低価格という点も魅力です。
経理におススメの資格

経理のキャリアアップに繋がる資格は、簿記関連の資格だけではありません。日商簿記以外の経理実務に役立つ資格を紹介します。
PASS(経理事務パスポート検定)
一般社団法人日本CFO協会が主催する「事務スタッフに求められる実践的な経理知識」を測る検定試験です。レベルは、3~1級までがあり、3級は「経理の役割や基本的な事務処理」、2級は「請求や支払、経費処理など経理の基本的な取引業務」、1級は「売掛金管理や固定資産管理、月次決算関連業務」などの学習範囲から出題されます。
未経験から経理を目指す方は、基本業務を覚えるためにチャレンジしてみると良いでしょう。
給与計算実務能力検定
一般社団法人実務能力開発支援協会が主催する給与計算のスキルレベルを測る検定試験です。
給与計算は、労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法などの法律に精通し、複雑な給与計算の仕組みを理解しておかなければならない専門性の高い業務です。
レベルは2級と1級があり、検定の勉強を通して、法律の知識や実際の給与計算を演習形式で学べます。
給与計算のスキルは、経理職のキャリアアップや転職活動でもプラスになるはずです。
ビジネス会計検定試験
大阪商工会議所が主催する「財務諸表の分析、財務状況を把握するスキル」を測る検定試験です。
3~1級までの等級があり、3級は「財務諸表の読み方や分析の基本」、2級は「財務諸表の応用分析や関連する法令の知識」、1級は「ディスクロージャー(企業の情報公開)や会計基準、内部統制」などが出題範囲に含まれます。
企業の財務状況を読み解くスキルが身につくため、財務に強くなりたい経理の方や、ゆくゆくは経営分析の道に進みたい方におススメです。
FASS(経理・財務スキル検定)
経理・財務の実務スキルを客観的に測ることができる、日本CFO協会主催の検定試験です。
合否ではなく、800点満点の総合点からE~Aの5段階でレベルが判定され、「資産分野」「決算分野」「税務分野」「資金分野」の4分野の達成度合いも確認することができます。
経理・財務部門の日常業務で使う実務に則した内容が多く出題されるため、スキルアップを目指す現役の経理・財務担当者が多く受検しています。
経理の資格に関するQ&A

-
Q.日商簿記の上位資格の取得必須?
A.経理のお仕事をするうえで、簿記の知識は欠かすことのできないものですが、「必ず日商簿記の上位資格を取得しなければならない」ということはありません。しかし、日商簿記の上位資格を持っていることでキャリアアップや転職の際に、大いに役立ちます。簿記初心者の方は、まず「日商簿記3級」を目指してみましょう。
-
Q.経理職の上級者を目指すときにおススメの資格は?
A.経理実務上級者へステップアップしたい方は、日商簿記検定1級や会計士・税理士などの資格取得を目指すのがおススメです。また、経理業務の中から得意分野を伸ばして関連する知識やスキルを取得すると、別のキャリアへの転向も可能になります。※関連記事:経理のキャリアアップとは?必要なスキルや経理のキャリアパスも解説! | みんなの仕事Lab-シゴ・ラボ-
※関連記事:「経理」と「財務」の違いって?業務内容と繁忙期、「会計」との違いについても解説 | みんなの仕事Lab-シゴ・ラボ-
資格を取得して、着実なキャリアアップを目指そう
経理の業務範囲は幅広いため、まずは現在の経験値やスキルのレベルを知り、キャリアアップのために必要な勉強や資格の取得を目指しましょう。そして、自分に合った学習方法や学習計画を立てて、着実に実行していくことが大切です。
今回紹介した、日商簿記などの経理関連資格や学習方法のポイントを参考に、今の自分に必要な知識・スキルを考えてみてください。なお、パソナでは登録スタッフの方が利用できる経理関連資格のeラーニングや、割引・特典が受けられる提携スクールのご案内も行っています。
働きながら、資格取得を目指せるプログラムが揃っていますので、ぜひチェックしてみてください。
パソナでは、経理事務を目指したい方を、種類豊富なオンライン講座や経理セミナーでサポートいたします。就業中のお悩みやキャリアアップなどもご相談ください!経理事務の魅力を知って、新たな一歩を踏み出してみませんか?
※関連ページ:経理の派遣の仕事一覧 | パソナJOBサーチ