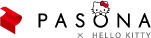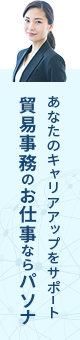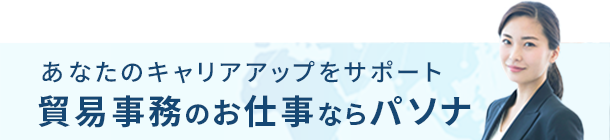アポストロフィー(’)記号の意味や使い方は?PCでの入力方法や種類について解説

アポストロフィー( ’ )の正しい使い方をご存知でしょうか?
「よく見かけるけれど、正しい意味は分からない」という方もいるでしょう。
アポストロフィー( ’ )は日本語に概念がないので、どのように使えば良いか迷ってしまいますよね。
今回は、意外と知らないアポストロフィー( ’ )の意味と、3つの用途「複数・所有・短縮」、PCでの入力方法について紹介します。
パソナでは、お仕事の悩みや疑問を未登録の方でもご相談できる、アバターキャリアコンシェルジュというサービスがあります。キャリアに関するご相談だけでなく、気軽なご質問やご相談も可能!キャリアコンサルタントがアバターを通じてご質問にお答えします。
- 目次
- アポストロフィー( ’ )とは
- 3つの用途「複数・所有・短縮」を理解すれば覚えやすくなる
- アポストロフィーは引用符として使うことも
- PC・スマホでアポストロフィーを入力する方法
- グローバルスタンダードを身につけよう
アポストロフィー( ’ )とは
アポストロフィー/apostropheとは、英語で使われる記号のひとつで、単語の冒頭、途中、最後のいずれかで使用されます。記号の形はカンマ( , )と同様ですが、アポストロフィー( ’ )は、文字の上端に記載します。
カンマ・ピリオド・コロン・セミコロンといった記号には同じ概念の日本語が存在していますが、
アポストロフィー( ’ ) には表記も概念も、日本語が存在しません。
3つの用途「複数・所有・短縮」を理解すれば覚えやすくなる
アポストロフィー( ’ )の使い方を理解するために、3つの用途に整理してみました。
簡単な用途から順に紹介していきます。
1. 複数を表す
複数形がない単語の場合、通常は単語の後に「s」をつけるだけで複数形になります。
例えば、“two days”(2日間)や “five plates”(お皿5枚)と表記します。
ですが、アルファベット(文字)を複数形にする時に、「s」をつけるだけでは誤読してしまいそうですよね。また、年代や世代を表すために数字を複数形にするときも、「s」をつけると複雑になります。そのため、アポストロフィー( ’ )をつけるのが一般的です。
アルファベット(文字)の場合
My name TANAKA has three A’s in it.
TANAKA(田中)にはAが3つあります。
数字の場合
I like 80’s music.
私は1980年代の音楽が好きです。
ただし、information、water、meat、paper、baggage、moneyなどの名詞には「’s」は不要です。
どれも数字で数えられない抽象的な単語(不可算名詞)ですので、1単語だけで数や大きさを示すことはできません。
“two bottles of water” “two sheets of paper” といったように、単位とともに表記します。
2. 所有を表す
所有格を表現するときは、「人」の後に「アポストロフィー( ’ )+ 小文字のs」 をつけます。
my father’s chair.
父のイス
my friend’s book.
友人の本
ただし、最後がsで終わる固有名詞にはアポストロフィーのみをつけます。
James’coat.
ジェームズのコート
また、所有代名詞(mine、oursなど)・所有限定詞(my、our、itsなど)など、すでに所有を表している単語には「’s」は不要です。
new bag of mine.
私の新しい鞄
length of a rack from its bottom to its top.
棚の上から下までの長さ
3. 短縮を表す
「主語+be動詞」
“I am ⇒ I’m”
“You are ⇒ You’re”
「主語+助動詞」
“He will ⇒ He’ll”
“I would ⇒ I’d”
「be動詞/助動詞の否定形」
“is not ⇒ isn’t”
“will not ⇒ won’t”
この他にも、「疑問詞 + be動詞 / have動詞」や、「助動詞 + have動詞」 など、短縮を表すアポストロフィー( ’ )にはたくさんの使い方があり、短縮で表せないケースもあります。
アポストロフィーは引用符として使うことも
アポストロフィーを引用符として、文や語句を囲って使う場合もあります。引用符とは引用や商品名、タイトルなどに用いる記号です。
※関連ページ:貿易事務のお仕事解説 | パソナIncoterms 2020’ was published on January 1, 2020.
2020年1月1日に『インコタームズ2020』が発行されました。
PC・スマホでアポストロフィーを入力する方法

最後に、PCやスマホでアポストロフィーを入力する手順や注意点を紹介します。
PCの場合、キーボードで「Shift」+「7」を押すとアポストロフィーが入力できます。
スマホのフリック入力の場合、iOSのキーボードでは「ABC」を押して入力モードを切り替えると、
最下段中央にアポストロフィーがあります。Androidのキーボードでは「123」を押して記号モードに切り替えると中央段にアポストロフィーがあるので、タップすると入力完了です。
PCのアポストロフィーには「直線型(’)」と「曲線型(’)」がある
PCでは「直線型」と「曲線型」という2種類のアポストロフィーを入力することができます。
直線型は左右で同じ形(”)になっていて、曲線型は左右で違う形(‘’)を持つことが特徴です。
英語では基本的に、直線型のアポストロフィーを使用します。英語入力モードで「Shift」+「7」を押したときに入力されるのも直線型です。
ただし、Wordのように自動校正機能があるツールを使うと、曲線型に自動で変換されることもあります。直線型にしたい場合は、自動校正機能をオフにして使用しましょう。
グローバルスタンダードを身につけよう
ビジネス英語では、主語や目的語をはっきり示すことが大切です。アポストロフィーを使いこなすことで、より伝わりやすいコレポンや英文書類が作成できるでしょう。
英文事務・外国語事務や貿易事務、外資系企業でのお仕事では、外国語スキルをはじめとするグローバルスタンダードが求められます。シゴ・ラボでは貿易会社や外資系企業のお仕事に興味のある方に役立つ情報を紹介していますので、ぜひ活用してみてください。
パソナでは、貿易事務を目指したい方へ、種類豊富なオンライン講座やセミナーでサポートいたします。就業中のお悩みやキャリアアップなどもご相談ください!貿易事務の魅力を知って、新たな一歩を踏み出してみませんか?